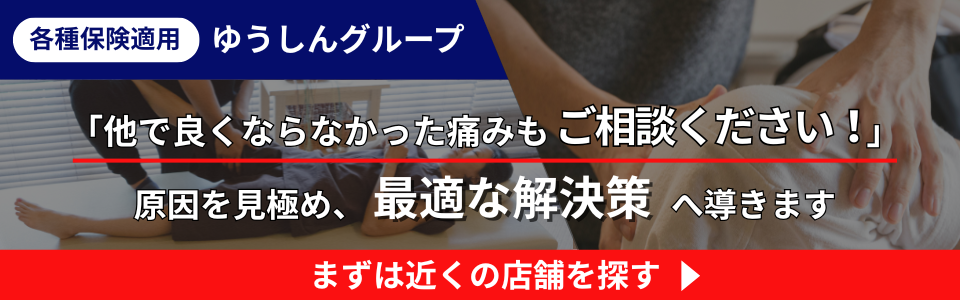鍼とマッサージの違いとは?期待できる効果やおすすめの人
最終更新日:2025.09.26
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
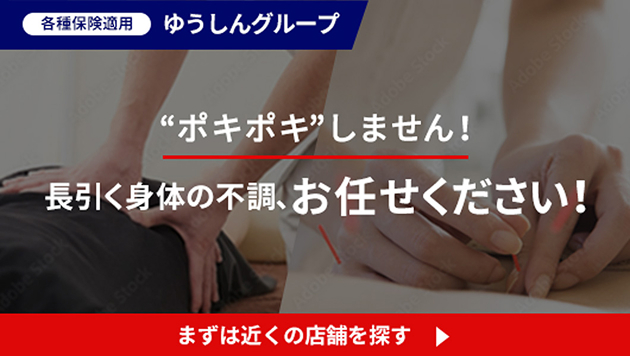

肩こりや腰痛、疲労感など、身体の不調に悩んでいるときの対処法として、鍼やマッサージがあります。利用してみたいとは思っているものの、鍼とマッサージはどう違うのか、どちらを受けるべきかわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、鍼とマッサージの違いや期待できる効果、おすすめの人の特徴などについて解説します。
目次
鍼とマッサージの違い

鍼とマッサージのどちらを受けるべきか決めるには、それぞれの特徴を把握することが重要です。まずは、鍼とマッサージの違いを解説します。
鍼:東洋医学の施術方法のひとつ
鍼とは、ステンレス製の鍼でツボを刺激して、身体の不調を改善する東洋医学の施術のひとつです。注射針よりも細い針を使用するため、施術の痛みはほとんど感じないといわれています。
なお、鍼の施術を提供したり鍼灸院を開院したりするには、「鍼灸師」の国家資格が必須です。鍼灸師の資格を取得するには、養成学校で知識と技術を学び、「はり師」と「きゅう師」の国家試験に合格する必要があります。
「はり師」と「きゅう師」はそれぞれ個別の資格ですが、両方の資格を取得する方が多いため、2つをまとめて鍼灸師と呼ばれるのが一般的です。
マッサージ:ヨーロッパ発祥の手技療法
マッサージは身体の表面をさする、揉む、押すなどして刺激し、血行や新陳代謝を促すことで身体の不調にアプローチするヨーロッパ発祥の施術です。
手技が基本であり、疲労回復やリラックス効果などが期待できます。
なお、日本でマッサージを行うには、「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格が必須です。あん摩マッサージ指圧師の資格を取得するには、所定の養成学校・施設で3年以上学び、あん摩マッサージ指圧師の国家試験に合格する必要があります。
鍼とマッサージで期待できる効果

鍼やマッサージを受けると、身体にどのような変化が起こるのでしょうか。ここでは、鍼やマッサージに期待できる効果について解説します。
鍼で期待できる効果
鍼の施術には、次のような効果が期待できます。
・血行を促進する
・免疫力の活性化を図る
・自律神経のバランスを整える
それぞれの効果について詳しく解説します。
血行を促進する
鍼には血管を拡張させて、血流を良くする効果があるといわれています。血管は全身に栄養や酸素を届ける役割と、老廃物を回収・排出する役割を担っている器官です。
鍼によって血流が改善されると、新陳代謝が促進されて疲れが取れやすくなったり、筋肉のダメージが回復しやすくなったりします。
また、身体が温まったり余分な水分が排出されやすくなったりするため、冷え性やむくみの緩和にも役立ちます。
免疫力の活性化を図る
鍼施術には、免疫力活性化の効果も期待できるとされています。鍼の刺激がサイトカインという免疫細胞を誘導する物質の産生を促し、免疫細胞を活性化させるからと考えられています。
免疫は体内に侵入した病原菌と戦い、身体を病気から守るための重要な機能です。鍼の施術によって免疫力が向上すれば、病気への抵抗力アップにつながります。
自律神経のバランスを整える
鍼には自律神経の働きを調整し、バランスを整える作用もあるといわれています。自律神経とは、生命維持に欠かせないさまざまな器官の働きを調整している神経です。
交感神経と副交感神経があり、交感神経は身体を活動的にする役割を、副交感神経は身体をリラックスさせる役割を担っています。
そのため、自律神経のバランスが乱れると、夜になっても身体がリラックスせず寝つきが悪くなるなど、さまざまな問題が発生するのです。
鍼によって自律神経が正常に働くようになれば、そうした自律神経の乱れが原因の問題が起こりにくくなります。
また、自律神経は精神面にも影響を与えており、自律神経が乱れると不安やストレス、イライラなどの精神的な症状が出ることがあります。自律神経のバランスが整えば、精神的な症状の緩和にもつながります。
マッサージで期待できる効果
マッサージには次のような効果が期待できます。
・リラックス作用を促す
・疲れを和らげる
上記の効果について詳しく解説します。
リラックス作用を促す
マッサージの施術を受けると、凝り固まった筋肉が緩んで血流が促進されます。すると全身に酸素や栄養が行き渡り、蓄積した疲労物質が排出されやすくなるので、身体の緊張がほぐれてリラックスしやすくなります。
疲れを和らげる
先述の通り、マッサージを受けると疲労物質が排出されやすくなります。また、長時間のデスクワークなどで固くなった筋肉が適度に揉みほぐされるので、疲れを和らげるのにも役立ちます。
鍼とマッサージ、それぞれどんな人におすすめ?

鍼とマッサージの特徴は理解できたものの、どちらを受けたら良いのか迷う方もいるでしょう。そこで、鍼とマッサージは、それぞれどのような人におすすめなのかを紹介します。
鍼がおすすめな人
鍼がおすすめなのは次のような人です。
・慢性化した痛みを和らげたい人
・自律神経の乱れを整え、バランスを調整したい人
鍼の施術では、ステンレス製の鍼で筋肉に直接刺激を与えます。問題の根本にアプローチするため、肩こりや腰痛などの慢性化した痛みの緩和を希望している方におすすめです。
また、鍼の施術には自律神経のバランスを整える効果も期待できるため、自律神経の乱れによる不眠や不安感などの不調に悩んでいる方にも向いています。
マッサージがおすすめな人
マッサージがおすすめなのは、次のような人です。
・日々の疲れを軽くしたい人
・ストレスを軽減したい人
マッサージを受けると緊張した筋肉が緩み、身体がリラックスしやすくなります。また、筋肉が緩んだことで血行が促進され、疲労物質が排出されやすくなるため、日々の疲れを取りたい方やストレスを軽減したい方におすすめです。
鍼・マッサージは保険適用の対象になる?
鍼やマッサージの施術を受けるときに、健康保険は適用されるのかが気になる方は多いのではないでしょうか。結論からいうと、鍼とマッサージのどちらも保険が適用されます。
ただし、すべての施術が保険適用になるわけではなく、所定の条件を満たさなくてはなりません。どのような場合に保険適用となるのか、鍼とマッサージの保険適用の要件について解説します。
鍼の場合
鍼の施術では、次の要件を満たす場合に健康保険が適用されます。
1.対象となる傷病に対する施術であること
2.鍼の施術を受けることについて、医師の同意を得ていること
要件1の「対象となる傷病」に該当するのは、以下の6つです。
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症
また、医師の同意については、対象となる傷病に対して医療機関で治療を行ったものの効果が得られなかったなどで、他に手段がないと判断された場合に限られます。
保険適用で施術を受けるには医師の同意書が必要なので、上記の傷病がある方で鍼の施術を受けたい場合は、まず医療機関で相談しましょう。
マッサージの場合
マッサージの場合は、次の要件を満たす場合に健康保険が適用されます。
・関節拘縮(※1)や筋麻痺(※2)などの症状があること
・関節の可動域を広げる、筋力を上げるなど、症状を改善する目的の施術であること
・マッサージを受けることについて、医師の同意を得ていること
健康保険は病気やケガの診療・治療費を補助するための制度であるため、リラクゼーションや疲労回復などが目的の場合は給付対象外です。
また、鍼の施術と同じく保険適用で施術を受けるには医師の同意書が必要なので、関節拘縮や筋麻痺の改善のために施術を受けたい場合は、先に医療機関で相談しましょう。
※1.かんせつこうしゅく:関節の可動域が制限され固定された状態
※2.きんまひ:神経の異常によって筋肉が硬直した状態
まとめ
鍼とマッサージは施術の方法や期待できる効果、必要な資格などが大きく異なります。また、保険適用で施術を受けるための要件も違うので、それぞれの特徴を把握して、どちらを受けるべきか判断することが大切です。
ゆうしんグループでは、独自のカウンセリングやAI姿勢分析システムを用いてお客様の身体の状態を判断し、適切な施術を提供しています。整体メニューもあり、さまざまな不調の緩和に対応可能です。
定期的な施術をサポートする独自システムをご用意しているほか、電話・メール・LINEでの予約が可能なため、通いやすい点も魅力です。自宅でセルフケアする方法もお伝えしていますので、身体の不調にお悩みの方はお気軽にご相談ください。