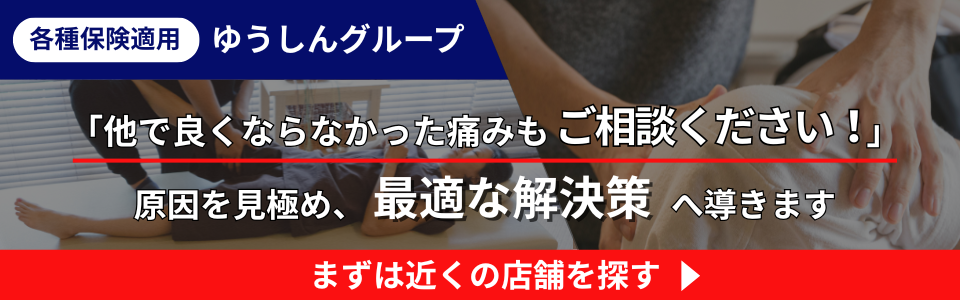肩こりによるめまいがつらい!めまいの原因や対処法を解説
最終更新日:2025.09.25
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
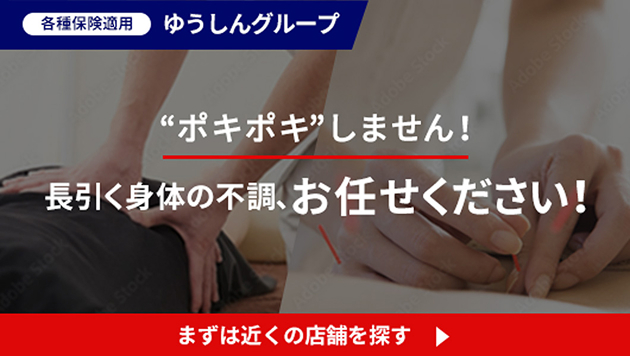

肩こりの症状がひどくなると、めまいが起こる方もいます。一見、肩こりとの因果関係はないように思えるめまいは、なぜ起こるのでしょうか。今回は、肩こりでめまいが起きる原因や、おすすめの対処法について解説します。
目次
肩こりでめまいが起きる原因

肩こりとめまいには、症状が現れる原因にいくつかの共通点があります。そのため「肩こりがひどいときに、めまいが起こる」と感じる方がいるのです。
肩こりでめまいが起こる主な原因は、次の4つです。
運動不足や身体の冷え
肩こりもめまいも、運動不足や身体の冷えによる血流悪化が原因の場合があります。血流が滞ると脳に酸素や栄養が行きわたりにくくなり、めまいにつながるのです。
血液が脳へ流れるとき、必ず通るのが首です。首には椎骨動脈という重要な血管のひとつがあるため、血流が悪くなると肩や首のコリにつながります。
肩や首のこり、めまいも、予防するためには首まわりの血流を滞らせないことが大切です。冬場の寒い屋外や真夏のエアコンが効きすぎたオフィスで長時間過ごすと、無意識のうちに肩や首の血流が滞りやすくなります。
長時間の同じ姿勢
長時間、同じ姿勢で過ごすと首から肩、背中にかけての筋肉が緊張して血流が滞りやすくなります。例えばPC作業などのデスクワーク、スマートフォンを使用するときなど、自分自身が思うよりも長時間同じ姿勢をとり続けているおそれがあります。
前述の通り、肩や首まわりの血流が滞ると脳への酸素や栄養供給に影響が出るため、コリ・めまいが生じかねません。
また、長時間同じ姿勢をとると、首の平衡感覚が正常に働かなくなり、めまいを起こす場合もあります。首には身体のバランスをとるための神経もあるため、長時間同じ姿勢でいたり過度なストレスを抱えたりすると、平衡感覚に影響を与えます。
悪い姿勢や猫背
悪い姿勢も、肩や首の筋肉に慢性的なストレスをかけるため、コリにつながります。猫背や巻き肩になっている方は、日常生活の中で肩や首の筋肉が緊張して凝りやすくなっています。
筋肉の役割は動作を助けるほか、姿勢の維持や血流を促進するなどさまざまです。悪い姿勢が続くと、身体のバランスをとるために一部の筋肉に負荷がかかります。
一時的なものであれば大きな心配はないですが、日常的に悪い姿勢が続くと筋肉を慢性的に緊張させます。筋肉が硬くなると血流も滞りやすく、神経系にも悪影響をおよぼします。
肩こり・首こりのほかに、自律神経の乱れに伴うめまい・吐き気といった症状が現れることもあるため、注意が必要です。
頚椎の問題
頚椎そのものに問題がある場合も考えられます。頚椎症など、首まわりの神経・血管に影響を与える症状がある方は頭部への血流が滞りやすく、めまい・ふらつきを起こすことがあります。
頚椎症とは、肩、首、腕、手などがしびれたり、運動障害が起こったりする症状のことです。椎間板の変形や退行性の変化によって、神経圧迫や血流障害が起こると、頚椎症につながります。
肩こりによるめまいが出たら病院へ受診すべき?
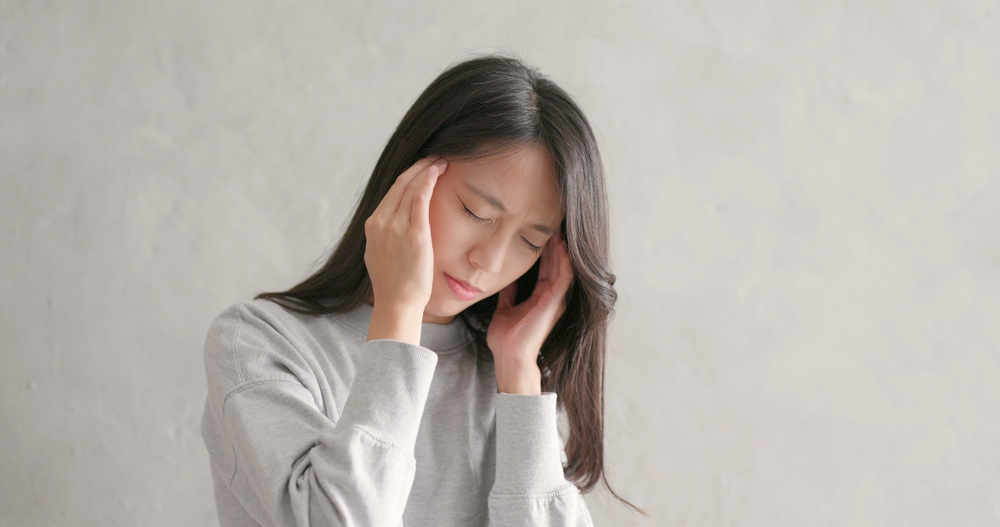
肩こりは、多くの方が一度は経験する症状です。身近に感じる症状だからこそ、病院に行くべきか様子を見るべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、肩こりによるめまいが出た場合、どのようなタイミングで病院を受診すべきか、何科へ相談するのが適切なのか解説します。
この症状は行くべきタイミング
以下のような症状がすでに出ている場合は、早めに病院を受診しましょう。
・日常生活に支障が出るほど強いめまい
・めまい以外の症状も出ている
・セルフケアを1週間続けても良くなる傾向がない
作業に集中できない、立ち上がったり歩いたりしにくいなど、日常生活に支障が出るほど強いめまいが出ている場合は、なんらかの異常が疑われます。肩こり以外の深刻な病気が隠れているおそれもあるため、早急に医師へ相談しましょう。
耳鳴り、頭痛、しびれといった、めまい以外の症状が出ている場合も早期の受診がおすすめです。
上記のような症状がなくても、1週間程度セルフケアを続けてみて良くならない場合は、一度医師に相談する選択肢もあります。なんらかの症状が出た際に受診することで、大きな病気の早期発見や対処にもつながるでしょう。
何科にいくべき?
肩こりによるめまいは、症状の強さや全身の状態によって受診すべき診療科が異なります。受診すべき診療科を見極めるポイントは、以下の通りです。
・整形外科:肩や首の痛みが強い。姿勢や動作に通常よりも制限がある
・耳鼻咽喉科:耳の症状・回転性めまいを起こしている
・神経内科:しびれ、ふらつき、頭痛などを伴っている
肩や首まわりの痛みが強いせいで普段どおりの姿勢をとれなかったり、動作に制限が出たりしている場合は、整形外科の受診がおすすめです。
耳の症状や回転性めまいが生じているときは、肩や首以外の場所に影響していたり、別の原因が隠れていたりするおそれがあるため、耳鼻咽喉科を推奨します。
しびれ、ふらつき、頭痛といった症状は、神経系の異常です。肩や首のコリに加えて、神経内科で神経系への影響を診てもらいましょう。
肩こりによるめまいへの対処法

肩こりによるめまいの原因には、前述の通り筋肉の緊張や血行不良などが関係している場合もあります。
ここでは、肩こりにともなう、めまいの対処法を解説します。
ストレッチをする
緊張した筋肉を無理に激しい運動で動かそうとしても、思うようには動作しません。ゆっくりとした動作で少しずつほぐしていく、ストレッチがおすすめです。
肩こりによるめまいの対処なら、僧帽筋上部線維ストレッチや胸張り運動が手軽に行えます。
僧帽筋上部線維ストレッチ
僧帽筋上部線維は、首から肩甲骨にかけて広がっている筋肉です。肩甲骨まわりの筋肉をほぐして可動域を広げると、血流を良くし筋肉の緊張を和らげられます。
首まわりの筋肉もほぐせるので、肩こり・めまいの両方に軽減が期待できます。
1.背中を丸めながら両手を前に出す。
2.胸を張って、両手を後ろに回す。
3.1~2をゆっくり繰り返す。
腕の動きに合わせて肩甲骨が開いたり寄ったりしているのを意識しつつ、上記の動作を繰り返します。肩甲骨を動かすためには、腕の付け根や背中の中心から動かすイメージで両手を前後させることがポイントです。
胸張り運動
多くの血管や神経が通っている首や後頭部は、日常生活のちょっとしたクセで緊張しやすい場所です。首や後頭部を意識した胸張り運動で筋肉をほぐし、自律神経を整えましょう。
1.左手を腰の後ろに回す。
2.右手で左側の肩を押さえる。
3.頭を右斜め下へ傾けて首を伸ばす。
4.数秒キープしてから頭を元の位置に戻す。
5.3~4を繰り返す。
6.左右を入れ替えて1~5を行う。
片手を肩に置く理由は、首を傾けたときに連動して上がらないようにするためです。首を曲げるときは、肩が上がらないように手でしっかりと押さえます。
ツボ押しをする
めまいを和らげる方法として、ツボ押しもおすすめです。めまい対策に向いているツボは、以下の2つです。
・風池(ふうち):後頭部の生え際で、耳の後ろのくぼんでいる部分
・合谷(ごうこく):手の甲側、親指と人差し指の骨が交わる位置にあるくぼみの部分
いずれのツボも、10秒程度押す動作を3セット行うと良いでしょう。
風池や合谷は、めまいだけでなく肩こりや頭痛の緩和にも有効とされています。ツボ押しの際には目を閉じて休むことで、目の疲れを和らげる効果も期待できます。
身体を動かす
運動不足は筋肉が硬くなり、血行不足につながります。日常的に適度な運動を行うことも、肩こりやめまい対策に効果的です。軽い運動は筋肉をほぐし、ストレス緩和や自律神経を整える効果も期待できます。
デスクワークや立ち仕事など、長時間同じ姿勢で過ごすことが多い方は、無意識のうちに筋肉が緊張しているおそれがあります。運動を意識して取り入れ、こまめに身体を動かすことが大切です。
姿勢を正す
肩こりによるめまいには、セルフケアに加えて症状が起こりにくい状態を維持する必要があります。筋肉を必要以上に緊張させないコツは、普段から正しい姿勢で過ごすことです。
猫背になることが多い方は、正しい姿勢を意識しましょう。筋肉の緊張がほぐれれば、肩こりによるめまいの予防や軽減につながります。
肩こりが気になる方はゆうしんグループへ
肩こり・首こりなど、背中周辺の痛みが続く場合は、「ゆうしんグループ」へご相談ください。
「ゆうしんグループ」は、痛みのない施術でお客様一人ひとりに合わせたアプローチを行います。カウンセリングを重視しており、プロの目線でお客様のお悩みに合ったセルフケアのアドバイスも行っております。
AI姿勢分析を導入していることも、「ゆうしんグループ」の強みのひとつです。データにもとづいた分析によって、より的確な施術を実現しております。
「最近、ちょっと肩まわりが重い」「肩が痛い日はめまいもする」とお悩みの方は、ぜひ一度「ゆうしんグループ」にお問い合わせください。
まとめ
肩こり・めまいに共通するのは、どちらも筋肉の緊張や血流の滞りが要因として考えられます。肩や首まわりの筋肉が緊張すると血流にも影響が出て、コリ・めまいにつながるのです。
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は、気付かないうちに肩や首まわりの筋肉を緊張させているかもしれません。手軽にできるストレッチでセルフケアしつつ、重い症状が続くときはプロへの相談も検討しましょう。