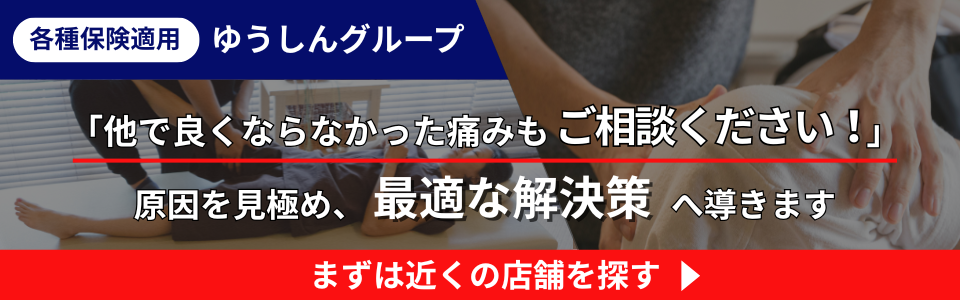冷えで足がつる原因とは?足がつったときの対処法・予防策を解説
最終更新日:2026.01.06
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
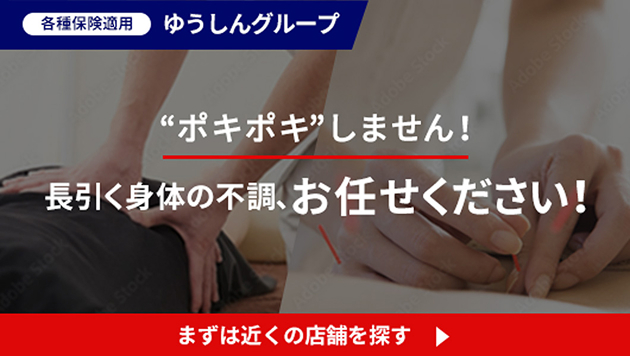

寒い季節になると「足がつりやすい」「夜中にふくらはぎが痛む」と感じる方も多いのではないでしょうか。その原因のひとつが“冷え”です。冷えは血流の悪化や筋肉の緊張、水分バランスの乱れを引き起こし、足のつりを招きます。
今回は、冷えで足がつりやすくなる原因や、実際につったときの対処法、そして日常生活でできる予防策について解説します。
目次
冷えで足がつりやすい原因

冷えと足のつりには密接な関係があります。冷えがもたらす血行不良や筋肉の緊張状態、水分バランスの乱れは、ふくらはぎや足先が急につることの原因です。
ここでは、それぞれの要因について詳しく解説します。
血行不良
冷えが強いと血管が収縮し、血液の巡りが悪くなります。その結果、足先まで十分な酸素や栄養が届かず、筋肉が正常に働きにくくなるため、つりやすくなるのです。
特に夜間は体温が下がりやすく、血流も滞るため、寝ている間にふくらはぎが急につることがあります。
さらに、血行不良は疲労物質の排出を妨げるため、筋肉の回復が遅れます。これが積み重なると慢性的に足がつりやすい状態になります。
筋肉の緊張
気温が低い環境では、身体が熱を逃さないように自然と筋肉を収縮させます。この反応が続くと筋肉が硬くなり、柔軟性を失った状態になりがちです。筋肉が緊張していると、ちょっとした動きや姿勢の変化でも強い収縮が起こり、足がつる原因になります。
特にふくらはぎや足裏は身体を支える役割が大きいため、冷えによる影響を受けやすい部位です。
長時間の立ち仕事やデスクワークで同じ姿勢を取り続けると、さらに緊張が強まり、つりやすい状況を招きます。
水分摂取量の低下
寒い季節は喉の渇きを感じにくく、水分摂取量が自然と減りがちです。
体内の水分が不足すると、ミネラルや電解質のバランスが崩れ、筋肉の収縮や弛緩を調整する機能がうまく働かなくなります。その結果、足がつりやすくなるのです。
また、冷えによって身体が余分な水分をため込もうとする働きが強まると、むくみや血液循環の悪化も生じ、足のつりを引き起こします。
冷えで足がつったときの対処法

突然足がつると、強い痛みで動けなくなることもあります。しかし、足のつりを早急に緩和する対処法を知っておけば安心です。
ここでは、すぐに実践できる方法を紹介します。
つったほうの筋肉を伸ばす
足がつったときは、つっている筋肉をゆっくり伸ばすことが基本です。まずはストレッチでつった状態を緩和しましょう。
【手順】
1.座った状態で深呼吸をして身体の力を抜く。
2.つった方の足の膝を伸ばして足首を立てる。
3.足の指をつかみ、身体の方へゆっくりと引き、ふくらはぎの筋肉を伸ばす。
4.筋肉のこわばりがとれるまでキープする。
一気に伸ばそうとせず、痛みが和らぐ程度の強さで数十秒かけて行うのがポイントです。急に強く引っ張ると筋肉を傷めてしまう可能性があるため、深呼吸しながらじわじわと伸ばす意識を持ちましょう。
冷えで硬くなった筋肉をゆっくり緩めることで、痛みの軽減につながります。また、足先に手が届かない場合は、タオルを足の指に掛けて同様にストレッチしましょう。
痛みが落ち着いたらマッサージをする
ストレッチで痛みが落ち着いたら、次はマッサージで筋肉をほぐします。両手でふくらはぎを包み込むようにし、下から上へ血流を促すように優しくさすります。円を描くようにほぐすのも効果的です。
マッサージを加えることで、血行の改善が期待できます。その結果、足のつりを防ぎ、冷えによる重だるさやむくみの改善にもつながります。
無理に強く押さず、心地よい圧で続けることが大切です。
市販薬を服用する
冷えによる足のつりが頻繁に起こる場合は、市販薬を活用するのもひとつの方法です。
特に漢方薬の芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)は、筋肉のけいれんや急な痛みに効果があるとされています。粉末や顆粒タイプで市販されており、症状が出たときに服用するのが一般的です。
ただし、芍薬甘草湯には「甘草(かんぞう)」という成分が含まれており、長期間または過剰に使用すると、むくみや高血圧などの副作用が現れることがあります。持病がある方や他の薬を服用している方は、事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
冷えで足がつらないようにするための予防策

足のつりを防ぐには、冷え性そのものを和らげる工夫が欠かせません。身体を温める習慣や運動、食生活の見直しなど、日常の積み重ねが予防につながります。ここでは効果的な方法を紹介します。
足を温める
冷えが原因で起こる足のつりを防ぐには、身体を内側と外側の両面から温めることが大切です。入浴時には、ぬるめのお湯に10~15分ほどつかることで血行が促進されます。足首までの部分浴でも十分な効果が期待できます。
また、就寝時には冷えやすい足先を守るために、靴下やレッグウォーマー、足ポケット付きの敷パッドを活用すると良いでしょう。
日中も、冷たい床に直接足が触れないようスリッパを履くなど、「足を冷やさない」意識を日常的に持つことが予防につながります。
運動習慣をつける
運動によって筋肉を動かすと血流が良くなり、冷えを防ぐ効果があります。
特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれるほど血液循環に関わる重要な部位です。そのため、ふくらはぎの筋肉をしっかり使うことで、血液の循環が促進され、冷えや足のつりの予防につながります。
ウォーキングや軽い体操など、日常的に取り入れやすい全身運動を続けることで、筋肉の柔軟性が保たれ、つりにくい状態を維持できます。
まずは簡単な運動を、無理のない範囲で始めてみましょう。
バランスの良い食生活を心がける
偏った食生活は冷えや筋肉の不調につながります。たんぱく質やビタミン、ミネラルを意識して取り入れることで、筋肉の働きや柔軟性を支えられます。
特にカルシウムやマグネシウム、カリウムは筋肉の収縮や弛緩に関わる栄養素です。そのため、ミネラルが不足すると足がつりやすくなります。冷えを和らげる食材として、根菜類や生姜など身体を温める食材も取り入れるとより効果的です。
水分補給を心がける
寒い時期は喉の渇きを感じにくく、意識的に水分を摂らなくなる傾向があります。寒さによって汗をかく量が減ることや、乾燥に気づきにくいことも要因です。
しかし、水分不足は血流を滞らせるだけでなく、体内の電解質バランスを崩し、足のつりを引き起こす原因になります。
健康な成人の場合、1日あたりの水分摂取量はおよそ1.5~2リットルが目安とされています。水やノンカフェインの飲み物をこまめに摂取することを心がけましょう。特に入浴の前後や就寝の前後に補給することが効果的です。
ふくらはぎのストレッチやマッサージをする
ふくらはぎは冷えの影響を受けやすく、筋肉が硬直すると足がつりやすくなります。日常的にストレッチやマッサージを取り入れることで、血流が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。
就寝前に足首を回す、ふくらはぎを伸ばすなどの軽いストレッチを行うだけでも効果的です。マッサージは下から上へさすり上げるようにすると血行が整い、冷えやむくみの予防にもつながります。
まとめ
冷えによる足のつりは、血行不良や筋肉のこわばり、水分・ミネラル不足が重なることで起こります。身体を温め、バランスの良い食事や水分補給、適度な運動を心がけることで予防が可能です。日々の生活習慣を見直し、冷えに負けない身体づくりをしていきましょう。
なかなか改善しないときは、専門家のアドバイスを受けてみるのもひとつの方法です。ゆうしんグループでは、冷えや血流不良からくる不調に対して、一人ひとりに合った施術や生活改善のサポートを行っています。お近くの店舗にぜひご相談ください。