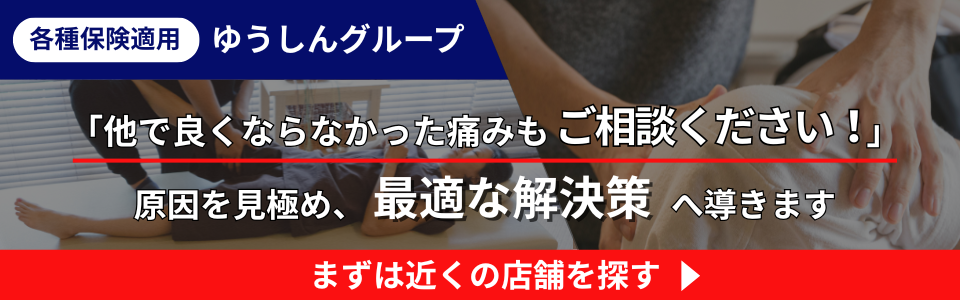【冷え性の男性必見】冷えの原因と症状を緩和するポイントを解説
最終更新日:2025.10.21
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
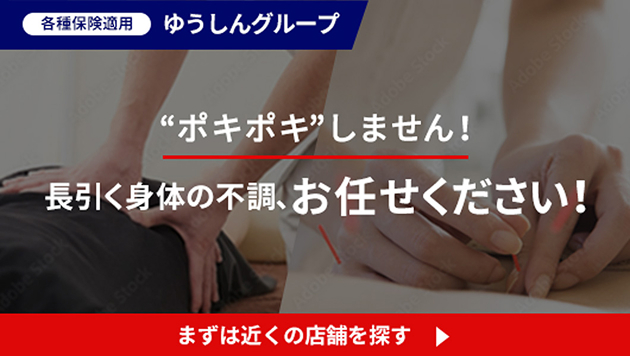

男性であっても冷え性に悩む方は少なくなく、その原因は基礎代謝の低下や運動不足、生活習慣の乱れなどさまざまです。手足の冷えを放置すると疲労感や集中力の低下、睡眠の質の悪化につながることもあります。では、どうすれば改善できるのでしょうか。今回は、男性向けに冷え性を改善するための具体的な方法について解説します。
目次
男性の冷え性は何が原因で起きる?

男性が冷え性になるのは、体質や一時的な生活習慣だけが理由ではありません。基礎代謝や筋肉量、ストレスや食生活など複数の要因が関わり合うことで症状が現れやすくなります。
ここでは主な原因を順に詳しく解説していきます。
基礎代謝の低下
男性でも年齢を重ねると筋肉量が減り、身体の熱を生み出す力が弱まっていきます。基礎代謝が落ちると、エネルギーを消費して体温を維持する機能が低下するため、手足の末端から冷えを感じやすくなります。
特にデスクワーク中心の生活では筋肉を使う機会が減り、代謝の低下が進みやすい傾向にあります。基礎代謝は体温維持の土台ともいえるため、冷え性改善のためには意識的に筋肉を維持する工夫が必要です。
運動不足
身体を動かさない生活が続くと、血流を促す筋肉のポンプ作用が弱まり、末端まで血液が届きにくくなります。
特にふくらはぎの筋肉は“第二の心臓”と呼ばれ、血液循環に大きく関与しています。運動不足によりこの働きが低下すると、血行不良が進み、冷えを感じやすくなります。
さらに、運動習慣の欠如はストレスの解消や基礎代謝の維持にも影響を与えるため、全身の冷えを招きやすい体質につながります。
食生活の乱れ
偏った食事や不規則な食生活は、身体のエネルギー不足を招き、冷えにつながります。特に、朝食を抜いたり糖質中心の食事が続いたりすると、熱を生み出す栄養素が不足して体温を維持しにくくなります。
また、アルコールやカフェインの過剰摂取も血流を悪化させる原因となります。これらの成分には血管を収縮させる作用や、利尿作用による体内の水分減少があるため、血液の巡りが悪くなり、結果として冷えを引き起こしやすくなります。
ストレス
強いストレスを受け続けると、自律神経のバランスが乱れ、血管の収縮や血流不良を引き起こします。交感神経が優位になりやすい状況が続くと、末端の血流が滞って冷えを感じやすくなるのです。
ストレスは精神的な負担だけでなく、身体の循環機能や代謝機能にも影響するため、リラックスできる習慣を持つことが冷え対策に役立ちます。
喫煙習慣
たばこに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、血流を悪化させます。その結果、末端まで血液が行き渡らず、冷えを感じやすくなります。
喫煙は一時的にリラックスできるように感じられるものの、実際には身体の循環機能を妨げ、冷え性を悪化させる原因にもなりかねません。
冷えに悩んでいる場合は、血流の改善を目的に禁煙を検討するのもひとつの方法です。
動脈に血栓ができる疾患
冷えの背後には、生活習慣や環境だけでなく、急性動脈閉塞症や閉塞性動脈硬化症といった疾患が関係している可能性もあります。
急性動脈閉塞症は、動脈に血栓が生じて血流が急激に遮断されることで、足先の冷えやしびれを引き起こします。
一方、閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化により足の血管が徐々に狭くなったり、詰まったりすることで血流が低下し、慢性的な冷えを招きます。
いずれも放置すると重症化するおそれがあるため、冷えが強く、長期間続く場合は早めに医療機関で診察を受けることが大切です。単なる体質だと決めつけず、病気のサインである可能性も念頭に置いておきましょう。
【男性向け】冷え症を改善するための方法

ここでは、冷え性を改善するための方法について詳しく解説します。
適度に運動する
冷え性を改善するためには、血流を良くすることが何よりも重要です。そのため、日常生活に運動を取り入れることが欠かせません。
特に、下半身の筋肉は全身の血液循環に大きく関与しており、ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は血流を促進する効果が期待できます。
さらに、スクワットや腹筋などの軽い筋トレを組み合わせることで筋肉量が増え、基礎代謝が上がり、身体の内側から熱を生み出しやすくなります。
激しい運動をいきなり始める必要はありません。例えば、通勤時に一駅分歩く、エスカレーターの代わりに階段を使うといった、日常のちょっとした工夫が冷えの改善につながります。
食生活を見直す
日々の食事は、冷え性の改善に深く関わっています。例えば、朝食を抜いてしまうと体温を上げるためのエネルギーが不足し、一日を通して冷えを感じやすくなります。
生姜やネギ、にんにく、唐辛子といった身体を温める食材を取り入れることに加えて、筋肉の材料となるたんぱく質や、血流をスムーズにする鉄分・ビタミンEなどをバランスよく摂取することが大切です。
水分補給をする
冷え性の人の中には「水分を摂ると身体が冷える」と考えて控える方もいますが、これは逆効果です。水分が不足すると血液の粘度が高まり、血流が滞って冷えを起こしやすくなります。
大切なのは、水分の“質”と“温度”です。冷たい飲み物ではなく、常温の水や白湯、温かいお茶などを選ぶことで、身体を内側から温めながら血行を促進できます。
特に、デスクワークの合間や入浴後などは水分が不足しがちなので、意識的にこまめな補給を心がけましょう。水分を定期的に摂る習慣をつけることで、体内の巡りが良くなり、冷えにくい状態を維持しやすくなります。
湯船につかって身体を温める
シャワーだけで済ませる習慣は冷え性を悪化させやすいため、湯船につかることを習慣化するのがおすすめです。全身をじっくり温めることで血管が広がり、血流が改善されます。
ぬるめのお湯(38~40度程度)に15分程度つかることで、副交感神経が優位になり、リラックス効果も高まります。
また、就寝前に入浴すると深部体温が下がるタイミングで眠気が促進されるため、質の良い睡眠につながります。
入浴剤やアロマオイルを使ってリラックス効果を高めるのも良いでしょう。
セルフマッサージを取り入れる

血流を促す方法としてセルフマッサージもおすすめです。特に冷えを感じやすい足先やふくらはぎを重点的にセルフマッサージすることで、滞っていた血流が改善され、温かさを実感しやすくなります。
オイルやクリームを使って肌の摩擦を抑えながら行うと、血流促進だけでなくリラックス効果も高まります。
また、セルフマッサージは筋肉の緊張をほぐすため、ストレスによる冷えにも有効です。
腹式呼吸でリラックスする
冷え性の改善には、自律神経を整えることも重要です。そのために役立つのが腹式呼吸です。深くゆっくりと息を吸い込み、腹部を膨らませながら行う呼吸法は、副交感神経を優位にして血管を拡張させます。
その結果、全身に血液が行き渡りやすくなり、冷えの緩和につながります。さらに、腹式呼吸にはリラックス効果があり、ストレスによる自律神経の乱れを防ぐ効果も期待できます。
仕事の合間や寝る前に数分間取り入れるだけでも、心身のバランスを整え、冷えに強い体質づくりに役立ちます。
まとめ
男性の冷え性は、基礎代謝の低下や運動不足、食生活の乱れ、さらにはストレスや喫煙など、複数の要因により起こります。放置してしまうと疲労感や集中力の低下、睡眠の質の悪化など、日常生活に大きな影響を与えるため、早めの対策が重要です。適度な運動や身体を温める食材の摂取、血行改善のためのセルフマッサージや入浴習慣は冷えの緩和に大きな効果があります。
こうしたセルフケアを日常に取り入れながらも、冷えが強く続く場合や不調が改善しない場合は、ゆうしんグループにご相談ください。
ゆうしんグループでは冷えに関連する不調の改善に向けた施術を提供していますので、お近くの店舗へお気軽にお問合せください。