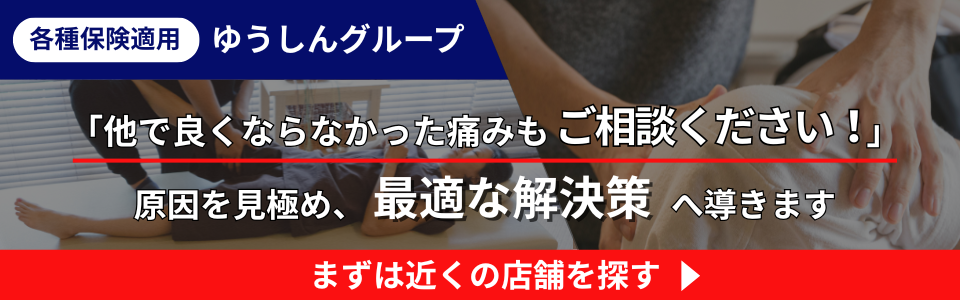冷えから頭痛が起きるのはなぜ?痛みの緩和方法や予防策を解説
最終更新日:2025.10.27
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
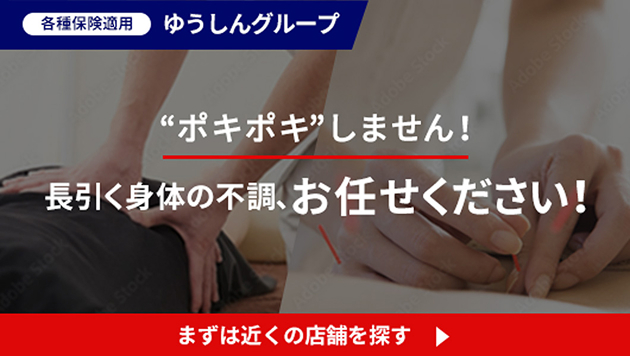

寒さや冷えを感じると、頭がズキズキと痛む――そんな経験はありませんか?実は、冷えが血流や自律神経のバランスを乱すことで、頭痛を引き起こすことがあります。原因を理解し、正しい対処を行うことで不快な痛みを防ぐことができます。今回は、冷えによる頭痛の原因と改善・予防方法について解説します。
目次
冷えで頭痛が起きる原因

冷えによる頭痛にはいくつかの要因が関わっています。血流の滞りや自律神経の乱れ、さらには体内の水分代謝の低下が複雑に影響し合うことで頭痛が引き起こされます。
ここでは主な原因について解説します。
血管の収縮・血行不良
身体が冷えると血管が収縮し、血流が悪くなります。この血流不足が筋肉のこわばりを招き、首や肩の筋肉が硬直して、頭痛の原因となることがあります。
特に冷え性の方は血流が滞りやすく、長時間のデスクワークや姿勢の乱れが重なると頭痛が悪化する傾向があります。
血行不良は脳への酸素供給も低下させるため、頭の重だるさや集中力の低下も引き起こします。冷えを和らげ、血流を促すことが緊張型頭痛を防ぐ第一歩といえるでしょう。
冷えによるストレス
寒い環境では、身体が熱を逃がさないように血管を収縮させます。
例えば、夏の冷房が効きすぎた環境は、身体に強いストレスを与え、自律神経のバランスを崩す原因となります。
また、冬場の冷えた寝室では、リラックスすべき夜でも身体が緊張してしまい、眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりするなど、睡眠の質に影響を及ぼします。睡眠の質が低下することで朝の寝起きに片頭痛を感じる人も増えます。
冷えによるストレスは自律神経を乱し、頭痛を引き起こしやすい体質へと変化させるため、身体を寒さから守る対策が大切です。
体内の水分バランスの乱れ
身体の冷えは、体内の水分バランスの乱れとも深く関係しています。特に運動不足や加齢による筋肉量の低下は、基礎代謝を下げる大きな要因です。筋肉は熱を生み出す役割を持っており、筋肉が減少すると体温が下がりやすくなります。
さらに、代謝が低下すると体内の水分循環が滞り、余分な水分が身体にたまりやすくなります。この状態を放置すると、冷えやむくみ、倦怠感といった不調が現れやすくなるのです。
水分の代謝がうまくいかないと、頭部の血管に水分が集まりやすくなります。その結果、血管が拡張して神経を圧迫し、ズキズキとした頭痛を引き起こすことがあります。特に冷え性の方は、血流が滞っているためにこうした症状が出やすい傾向があります。
冷えによる頭痛を緩和する方法

冷えによる頭痛にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因や対処法が異なります。
代表的なのは「緊張型頭痛」と「片頭痛」です。
緊張型頭痛は、首や肩の筋肉がこわばることで起こりやすく、血行不良や姿勢の乱れが影響するとされています。一方、片頭痛は脳の血管が拡張することで生じると考えられており、ストレスやホルモンの変化、冷えなどが誘因になることがあります。
ここでは、こうしたタイプごとの違いに合わせたケア方法や、日常でできるセルフケアの工夫について解説します。
緊張型頭痛の場合
冷えによって首や肩の筋肉がこわばり、血流が悪くなると、緊張型頭痛が生じやすくなります。そのため、温めて血行を促すことが効果的です。
蒸しタオルを首筋や肩に当てると筋肉がゆるみ、頭の重だるさが軽減しやすくなります。
また、身体の内側から温めることも大切です。白湯やノンカフェインのハーブティーは、体温を穏やかに上げ、リラックスにもつながります。
普段から冷えをためこまない生活習慣を心がけることが、頭痛の予防にも役立ちます。
片頭痛の場合
片頭痛は、冷やすケアが向いているとされます。血管の拡張が関係しているため、こめかみや首筋を冷やすことで血管を収縮させ、痛みがやわらぐことがあります。
また、コーヒーや紅茶に含まれるカフェインには血管収縮作用があるとされており、片頭痛の緩和に役立つ可能性があります。適量を摂取することでリラックス効果も得られるとされ、セルフケアのひとつとして取り入れてみるのも良いでしょう。
ただし、カフェインの摂取は睡眠に影響を与える可能性があるため、できるだけ午前中までにとどめるのが望ましいでしょう。
頭痛に働きかけるツボを刺激する
ツボ押しも、冷えによる頭痛のセルフケアとして役立ちます。
緊張型頭痛には、後頭部の髪の生え際あたりにある「風池(ふうち)」がおすすめです。親指でゆっくり押すと、首や肩の緊張がほぐれていきます。
一方、片頭痛には、手の甲側で親指と人差しの骨が交わるところにある「合谷(ごうこく)」が有効とされており、血流や自律神経のバランスを整える作用があります。
ツボ押しは道具も要らず、いつでもどこでも簡単にできる方法です。ご自身の症状に合わせて試してみることで、頭痛の予防や軽減につながるでしょう。
市販薬で対処する
冷えによる頭痛がつらいときには、市販薬を利用するのもひとつの方法です。即効性を求める場合は頭痛薬で痛みを抑えることができますが、繰り返す頭痛に悩む方には漢方薬も選択肢になります。
例えば、身体の冷えや水分代謝の乱れを整える漢方は、頭痛の原因にアプローチしてくれます。自分の体質や頭痛のタイプに合った薬を選ぶことが重要なため、症状が長引く場合は医師や薬剤師に相談するのが安心です。
冷えによる頭痛の予防策

冷えからくる頭痛を防ぐためには、日常生活の中で身体を温め、血流や自律神経のバランスを整えることが大切です。ここでは効果的な予防策を紹介します。
適度な運動をする
運動は冷え性の改善に欠かせません。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を習慣にすると、血流が促進されて身体の隅々まで酸素が行き渡ります。その結果、筋肉のこわばりも和らぎ、緊張型頭痛の予防につながります。
さらに、運動によって基礎代謝が上がるため、体温が下がりにくくなり冷えにくい身体づくりが可能です。無理な運動をする必要はなく、日常の中に軽い動きを取り入れることが効果的です。
血行を良くする食材を摂る
食事も冷えによる頭痛予防に大きな役割を果たします。身体を温める食材や血流を良くする食材を積極的に摂ることで、冷え性の改善が期待できます。しょうがやねぎ、にんにくなどは身体を温める代表的な食材です。
また、魚やナッツに含まれるオメガ3脂肪酸は血液の流れをスムーズにし、頭痛の予防に役立ちます。日々の食生活に取り入れることで、体質そのものを改善し、頭痛の起きにくい身体をつくることができます。
十分な睡眠を取る
睡眠は身体を回復させるだけでなく、自律神経を整える大切な役割を担っています。質の良い睡眠を確保することで、血流の低下やストレスによる頭痛のリスクを減らせます。
冷え性の方は就寝時に身体が冷えて眠りが浅くなりやすいため、寝具や衣類で身体を温める工夫も必要です。睡眠の質を高めることで体内リズムが整い、冷えに伴う頭痛の予防につながります。
まとめ
冷えによる頭痛は、血行不良や血管の拡張、水分バランスの乱れなど、さまざまな要因が複雑に関係して引き起こされます。
緊張型頭痛は、筋肉のこわばりが主な原因となるため、身体を温めて血流を促すことが効果的です。一方で、片頭痛は血管の拡張が関与しているとされ、冷却やカフェインの摂取などが症状の緩和に役立つ場合があります。
そのほかにも、市販薬や漢方、ツボ刺激など、セルフケアによって症状を和らげる方法もあります。冷えそのものを改善するには、運動や食生活、睡眠など、生活習慣を整えることが重要です。
もしセルフケアだけでは改善が難しいと感じた場合は、専門的なサポートを検討してみるのもひとつの方法です。
ゆうしんグループでは、体質改善を中心に、冷えや頭痛に悩む方へのサポートを行っています。まずはお気軽に、お近くの店舗へご相談ください。