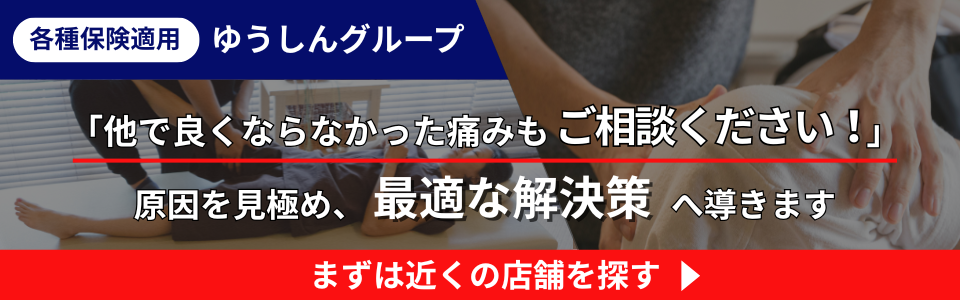肩甲骨はがしで期待できる効果とは?初心者向けにやり方を解説!
最終更新日:2025.08.22
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
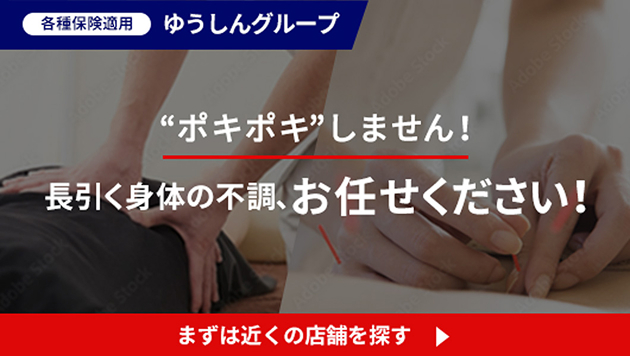

首や肩の不調に肩甲骨はがしが良いと聞いたことがあるものの、実際にはどのような効果があるのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。肩甲骨はがしは正しく行えば、姿勢改善や代謝向上など、さまざまなメリットが期待できます。
そこで今回は、肩甲骨はがしで期待できる効果を詳しく解説した上で、正しいやり方やポイントを紹介します。道具を使わず、自宅で簡単にできる方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
肩甲骨はがしとは?

肩甲骨はがしとは、肩甲骨まわりの筋肉をほぐし、可動域を改善するストレッチや体操のことです。
現代人の多くは、首こりや肩こり、猫背のような不良姿勢を抱えがちです。これは長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などによって、肩甲骨が本来の正しい位置から外側に開き、背中が丸くなった状態になってしまうからです。
この状態が続くと、肩甲骨まわりの筋肉が硬くなり、血行不良からさまざまな不調を引き起こします。
肩甲骨はがしを行うと筋肉の柔軟性が高まり、血行も促進されます。その結果、首や肩のコリ、猫背、四十肩・五十肩などの軽減・予防にもつながるとされています。
「はがし」という言葉は少し怖く感じる方もいるかもしれません。
しかし、肩甲骨はがしは、ゆっくりと筋肉を伸ばしたり、肩甲骨を大きく動かしたりして、固まった筋肉をほぐしていく優しい施術なのです。
肩甲骨はがしで期待できる効果とは?

肩甲骨はがしには、以下のような効果が期待されています。
・首こり・肩こりの改善・予防
・姿勢改善
・冷え・むくみ改善
・基礎代謝の向上
これらの効果について詳しくみていきましょう。
首こりや肩こりの改善・予防
肩甲骨はがしで筋肉がほぐれて血流が良くなると、痛みの原因となる発痛物質が溜まりにくくなり、首・肩のコリの改善が期待できます。
また、肩甲骨の動きがスムーズになるため、筋肉のこわばりからくる不調の予防にも効果的です。
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって、首の付け根や肩だけでなく、背中にまで不調を感じている方もいます。強い張りや重だるさに加え、「鉄板が入っているよう」と表現されるほどの不快感を抱える方も少なくありません。
肩甲骨はがしを継続的に行うことで、筋肉の柔軟性が向上し、つらい症状の軽減に加えて、再発を防ぐ手助けにもなります。
姿勢改善
筋肉の緊張がほぐれることで、肩甲骨の可動域が広がり、猫背や巻き肩などの不良姿勢の改善につながります。
特に、背中の筋肉である菱形筋(りょうけいきん)や僧帽筋(そうぼうきん)が柔らかくなると、背骨に沿って肩甲骨が近づき、本来の正しい位置に近づきやすくなります。
また、姿勢が改善されると胸が開いて上を向くようになるため、鎖骨がはっきりと見え、フェイスラインが引き締まりやすくなるのもメリットです。
さらに、猫背のような前かがみの姿勢は実年齢よりも老けて見られることがありますが、肩甲骨はがしを行うことで、全身の姿勢が改善され、若々しい印象を与えることができます。
冷え・むくみ改善
肩甲骨はがしには、冷えやむくみの改善も期待できます。肩甲骨まわりの筋肉がゆるむことで血流が促進され、手足の末端にまで血液が巡りやすくなるためです。
さらに、肩甲骨が正しい位置に近づくと胸が開き、深い呼吸がしやすくなります。その結果、酸素が全身に行き渡りやすくなり、代謝が高まって、冷えやむくみの予防にもつながるのです。
基礎代謝の向上
肩甲骨まわりの筋肉がほぐれて可動域が広がると、普段あまり使われない筋肉も働きやすくなり、基礎代謝の向上が期待できます。
この働きによってエネルギー消費が高まるため、背中や二の腕などに脂肪がつきにくくなる効果も期待されます。
さらに、肩甲骨の柔軟性が保たれて関節の動きが滑らかになり、骨同士の衝突を防げるため、四十肩・五十肩の予防にもつながります。
肩甲骨はがしのやり方

道具を使わず手軽にできる、肩甲骨はがしのストレッチを4種類紹介します。各ストレッチは、1回10~15秒を目安に3回ずつ行いましょう。片側ずつ行う場合は、左右それぞれ3回ずつ実施してください。
起床時や就寝前、仕事の合間などのタイミングで、1日2~3セット取り入れるのがおすすめです。
基本のストレッチ
まずは基本のストレッチをみていきましょう。
<手順>
1.片腕を背中に回し、手の甲を腰に軽く当てる
2.肘または手首を、もう一方の手で持ち、背骨の方向へ引く
<ポイント>
胸を開き、背筋をまっすぐに保ちながら行うのがコツです。肩が前に出たり背中が丸まったりしないように意識し、肩甲骨が内側に寄る感覚を大切にしましょう。
また、痛みが出ない範囲で、呼吸を止めずにゆっくりと行います。
背面で指を組むストレッチ
両手を組み、前屈して行うストレッチです。
<手順>
1.足を肩幅より広めに開いて立つ
2.両手の指を背中で組み、腕を後ろにまっすぐ伸ばす
3.腕を挙げながら、上半身をゆっくり前屈させる
4.腕の重みを利用しつつ、頭を下げながら前屈を深める
<ポイント>
腕と身体の角度は90度を意識しましょう。勢いをつけずに、腕の重さを利用して自然に前屈するのがポイントです。
壁を使ったストレッチ
腕を壁に固定して前屈するストレッチです。
<手順>
1.壁のコーナーに立ち、肘を直角に曲げて腕を肩の高さまで挙げる
2.腕を壁につけたまま、上半身を前屈していく
<ポイント>
指先から肘まではしっかりと壁に密着させて行いましょう。また、立ち位置を変えずにゆっくりと前屈し、肩甲骨がじんわりと伸びる感覚を意識します。
肩甲骨を寄せるストレッチ
最後に、椅子に座ったまま行えるストレッチを紹介します。
<手順>
1.肘を直角に曲げて肩の高さまで挙げ、前で腕を合わせる
2.そのまま両腕を開き、肩甲骨を背骨に寄せるイメージで動かす
3.両腕をバンザイさせ、頭の上で両手の甲を合わせる
4.ゆっくりと腕を下ろし、2の姿勢に戻す
5.1の姿勢に戻す
<ポイント>
肩甲骨を背骨に寄せるように意識して行いましょう。
肩甲骨はがしをする際の注意点
肩甲骨はがしは自分でも取り組めるストレッチですが、効果を高め、安全に行うためにはいくつかの注意点があります。無理をせず、正しい方法で、自分の身体にあったやり方を選びましょう。
ここからは、肩甲骨ストレッチを行う前に知っておきたいポイントを、3つに分けて解説します。
無理をしない
筋肉や関節に負担がかかると、痛みが悪化したり、ケガにつながったりする可能性があります。そのため、無理に強く動かすのは避けましょう。特に首や肩に痛みがある場合は、動作をゆっくりと優しく行ってください。
また、「痛ければ効いている」と誤解して無理をしてしまう方もいますが、肩甲骨はがしは我慢して行うものではありません。無理のない範囲で、心地良く続けることが大切です。
正しく行う
肩甲骨はがしは、自己流でなんとなく動かしているだけでは十分な効果が得られないどころか、筋肉や関節を痛める原因にもなります。効果的に行うためには、正しい姿勢と動かし方を理解しましょう。
信頼できる情報源を参考にしたり、専門家のアドバイスを受けたりすると安心です。
自分に合った方法を選ぶ
肩甲骨ストレッチは、自分に合った方法で行ってください。特に高血圧や心疾患のある方は、急激な動作や強い負荷をかけると、身体に負担がかかるおそれがあります。
不安がある場合は自己判断で行わず、医師や理学療法士などに相談しましょう。自分の体調や体力に合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。
まとめ
肩甲骨はがしには、肩・首のコリや猫背などを改善し、血流や代謝を促す効果が期待できます。毎日の習慣に取り入れることで、その効果を実感しやすくなります。
ただし、より良い効果を得るには、無理をせず正しい方法で行いましょう。専門家のアドバイスを受けながら、自分の状態に合わせて継続してみてください。
ゆうしんグループでは、AI姿勢分析システムでお客様の身体の状態を判断し、痛みのないソフトな施術を心がけています。また、一人ひとりに合った施術を提供するため、丁寧なカウンセリングを重視しています。
自宅で行えるセルフケアのアドバイスもしていますので、首や肩まわりの不調にお悩みの方はお気軽にご相談ください。