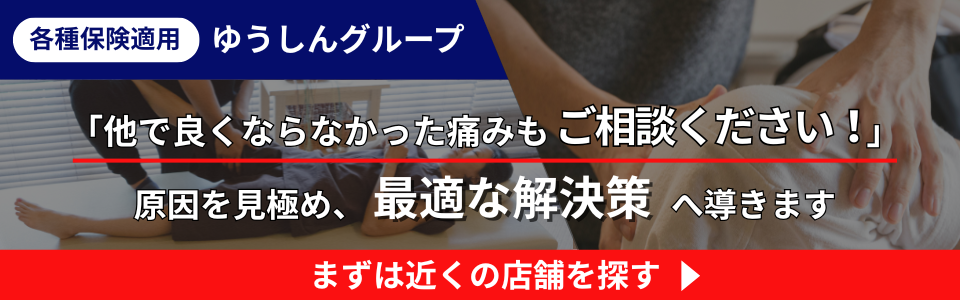肩甲骨が痛いのはなぜ?対処法と肩まわりを整えるストレッチも紹介
最終更新日:2025.10.21
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
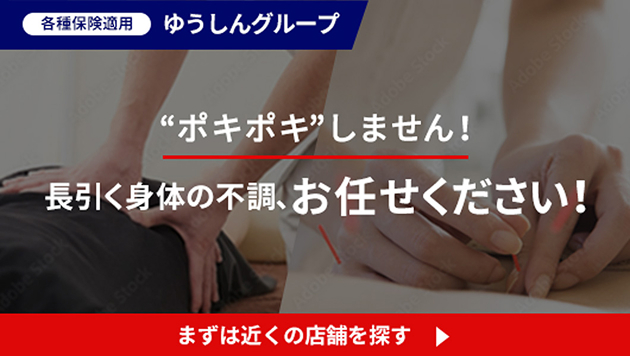

肩甲骨まわりに痛みを感じると、仕事や日常生活に支障が出て不安になる方も多いのではないでしょうか。肩甲骨の痛みは、姿勢や筋肉の不調だけでなく内臓疾患が関係している場合もあります。今回は、肩甲骨の仕組みや痛みの原因、改善に役立つ対処法やストレッチについて解説します。
目次
肩甲骨の仕組みについて

肩甲骨は、背中の左右に位置する三角形の平らな骨で、体幹には直接固定されず、筋肉によって支えられる“浮遊構造”を持っています。
この独特な構造により高い可動性が実現されており、腕を前後・上下に動かすことや回旋運動など、さまざまな動作において重要な役割を果たしています。
肩の動きは鎖骨・上腕骨・肩甲骨の3つの骨が連携して行われ、私たちの日常生活や仕事での動作を支えています。
一方で、可動域が広いぶん安定性には欠けており、筋肉や靭帯によるサポートがなければ十分に機能しません。長時間の使用や急激な動作、反復動作により、肩甲骨周辺は疲労しやすく、痛みや不調が生じやすい部位です。
特に、デスクワークやスマートフォンの長時間使用といった現代的な生活習慣は、肩甲骨への負担を増大させる要因となっています。
さらに、肩甲骨は単に肩の動作を担うだけでなく、呼吸とも密接に関係しています。呼吸時には肋骨や背部の筋肉と連動して動くため、肩甲骨の可動性が低下すると呼吸が浅くなり、結果として疲労感や集中力の低下につながる可能性もあります。
肩甲骨まわりが痛い原因

肩甲骨の痛みには複数の要因があります。ここでは筋肉・関節の問題と、内臓の不調による関連痛の2つの側面から説明します。
筋肉や関節まわりの不調
加齢や日常の習慣により筋肉の柔軟性や弾力が失われると、炎症や痛みが生じやすくなります。特に肩こりや四十肩・五十肩といった肩関節周囲炎は代表的な例で、肩甲骨の動きが制限されることもあります。
さらに、肩腱板断裂や肩鎖関節脱臼、石灰性腱炎などの疾患では、強い痛みや腕の可動域制限が伴うケースもあります。このような疾患は一度だけでなく、慢性的な負担の積み重ねで発症することも多いため注意が必要です。
また、スポーツや肉体労働で肩を酷使する人に多いのがオーバーユース(使いすぎ)による炎症です。繰り返しの動作で肩甲骨まわりの筋肉が疲労し、痛みが出てしまうケースも少なくありません。
内臓の不調
肩甲骨の痛みは必ずしも筋肉や関節に限られたものではありません。首の疾患である変形性頚椎症や椎間板ヘルニアはもちろん、心臓病や胆嚢・胆管の疾患、さらには気胸といった胸部の異常が関連痛として肩甲骨に現れることがあります。
これらはいわゆる放散痛で、肩自体に異常がなくても痛みが出るのが特徴です。痛みが長引く、呼吸や動悸、発熱など他の症状を伴う場合は、早めに病院を受診することが重要です。
肩甲骨の痛みが気になる場合の対処法

肩甲骨の痛みは生活習慣を整えることで軽減できる場合もあります。ここでは日常で取り入れやすい対処法を紹介します。
姿勢を整える
まず意識したいのは姿勢です。猫背や反り腰などの歪んだ姿勢は、肩甲骨まわりに過度な負担をかけます。また、デスクワークやスマートフォンの使用で同じ姿勢を長く続けることも筋肉の緊張を高め、痛みを悪化させます。
正しい姿勢を維持するためには、椅子や机の高さを見直すことや、足を床にしっかりつけるなどの工夫も大切です。背筋を伸ばし、左右の肩をバランスよく使う意識を持つことで、痛みの予防や改善につながります。
適度な運動を心がける
肩甲骨まわりの筋肉を動かすことで血流が改善し、筋肉疲労やコリの改善が期待できます。毎日の軽いストレッチやウォーキング、肩を回す運動など、簡単に取り入れられる動作で十分です。継続して行うことがポイントになります。
特にデスクワークの合間に短時間でも体を動かす習慣を持つことが、慢性的な肩甲骨の痛みを防ぐカギになります。
肩まわりを冷やす・温める
肩まわりに痛みがある場合は、患部の状態に応じて「冷やす」または「温める」ことで対処が可能です。それぞれの適切な方法を以下に説明します。
■腫れや熱感が見られる場合
肩に腫れや熱感が見られる場合、炎症が生じている可能性があります。このような場合は、肩まわりを冷やして炎症を抑えることが有効です。
冷却には、冷たいタオルや市販の冷却シートの使用が推奨されます。アイスパックを使用する際は、凍傷を防ぐために必ずタオルやハンカチで包み、直接肌に触れないようにしてください。
冷やす時間の目安は10~15分程度です。ただし、長時間の冷却は血行不良を引き起こすおそれがあり、症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。
■腫れや熱感がない場合
腫れや熱感などが見られない場合は、温めることで血流を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待されます。
具体的には、入浴による温熱療法や、蒸しタオル、使い捨てカイロの使用などがあげられます。ただし、カイロを直接肌に長時間当てると低温やけどのリスクがあるため、使用時には注意が必要です。
なお、冷え性の方や寒い季節には、こうした温熱ケアを意識的に取り入れることで、血行不良による肩のこわばりや不快感の軽減につながる可能性があります。
市販薬の使用を検討する
痛みが強いときには市販薬の利用も選択肢のひとつです。消炎鎮痛成分を含む塗り薬や湿布、ロキソプロフェンやイブプロフェンといった内服薬で炎症を和らげることができます。
また、神経や筋肉の働きをサポートするビタミンB群やEを含むサプリメントも有効な場合があります。自己判断で長期使用せず、症状が改善しない場合は医療機関へ相談しましょう。
肩甲骨の痛みの緩和におすすめのストレッチ
肩甲骨の可動域を広げるためのストレッチは、痛みの軽減や予防に役立ちます。ここでは簡単に取り入れられるストレッチを紹介します。
肩甲骨を大きく動かすストレッチ
肩を前から後ろへ、後ろから前へと大きく回す「肩回しストレッチ」は基本的で効果的な方法です。肩甲骨の動きを意識して行うことで、筋肉の緊張をほぐし、血流が促進されます。
【手順】
1.背筋を伸ばして立ち、両手の指先を同じ側の肩の上に軽く置く。
2.指先を肩から離さないようにしたまま、両肘を前→上→後ろ→下へと大きく円を描くように動かす。
3. ゆっくりとしたペースで、肩甲骨が動いているのを感じながら10回回す。
4. 今度は逆方向に回し、肘を後ろ→上→前→下へと動かし、10回繰り返す。
毎日の習慣に取り入れることで、肩甲骨まわりの柔軟性が高まります。座りながらでもできるため、仕事の合間やお風呂上がりなど、リラックスしたタイミングに行うと続けやすいでしょう。
胸を開くストレッチ
デスクワークで猫背気味の方に適したストレッチです。両腕を後ろで組み、胸を開くように背中を反らすことで肩甲骨が自然に寄せられます。このストレッチで胸郭も広がり、呼吸も深くなりやすい点が特徴です。
【手順】
1. 両足を肩幅程度に軽く開いて立ち、背筋を伸ばす。
2.両手を身体の後ろに回し、腰より少し上の位置で親指が背中に着くように指を組む。
3.組んだ手の手のひらが下になるようにひっくり返す。
4.そのまま腕を下へ伸ばし、胸と背中を伸ばす。
5. あごを上げて斜め上を見るようにし、胸が最大限開いた状態で15秒間キープする。
痛みがあるときは無理をせずにできる範囲で行いましょう。また、キープしているときは呼吸を止めないように注意してください。
また、長時間の座位により腰まわりが硬くなってる方や、腰痛がある方は腰をさらに痛める可能性があるため、控えるのが望ましいです。
長時間のパソコン作業の合間に取り入れると、肩甲骨の痛み予防に役立ちます。
タオルで簡単!肩甲骨のストレッチ
タオルを両手で持ち、上下に引っ張りながら腕を動かすストレッチも効果的です。肩甲骨を大きく動かせるため、柔軟性を取り戻せます。
【手順】
1.背筋を伸ばす。
2.タオルの両端を持ち、腕を前に出す。
3.そのまま腕を上に上げバンザイの形にする。上げた腕はできるだけ耳の後ろにくるようにする。
4.伸ばした腕を元の位置に戻し、タオルが首の後ろに来るようにする。
5.3~4の動作を10回繰り返す。
肩は上げず、背中が丸まらないようにし、2~3セット行うのが目安です。特別な道具を必要としないので、肩甲骨の痛みを感じたときにすぐ実践できます。
肩甲骨の痛みが改善されない場合はゆうしんグループへご相談ください
セルフケアやストレッチを続けても肩甲骨まわりの痛みが改善しない場合、専門家に相談することが解決への近道です。
ゆうしんグループでは、痛みの少ない施術に加え、カウンセリングを丁寧に行い、一人ひとりに合った改善方法を提案しています。さらに、AI姿勢分析を導入しているため、客観的なデータに基づいたアプローチが可能です。
慢性的な痛みを放置すると、姿勢の崩れや可動域の制限が進行し、肩以外の腰や首にも影響が出てくることがあります。肩甲骨まわりの不調は全身のバランスと直結しているため、早期に対応することが将来の健康維持にもつながります。
肩甲骨の違和感や痛みが続くときは、我慢せず「ゆうしんの店舗一覧」から最寄りの店舗を確認しご相談ください。
まとめ
肩甲骨は腕や体幹の動きを支える重要な骨であり、自由度が高い分、筋肉や関節に負担がかかりやすく、痛みを感じやすい部位です。姿勢の乱れや長時間の同じ姿勢、加齢や疲労の蓄積などが原因となることが多く、生活習慣の工夫やストレッチで改善できるケースもあります。
ただし、内臓疾患などが関係している場合もあるため、痛みが長引くときは自己判断せず専門家への相談が大切です。日常のケアと適切な対応で、健やかな肩の動きを取り戻していきましょう。