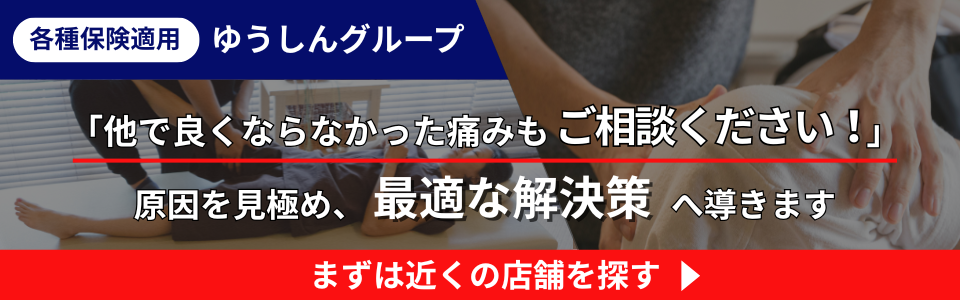ぎっくり腰になったら絶対NGな行動4つと正しい予防法3選
最終更新日:2025.07.24
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
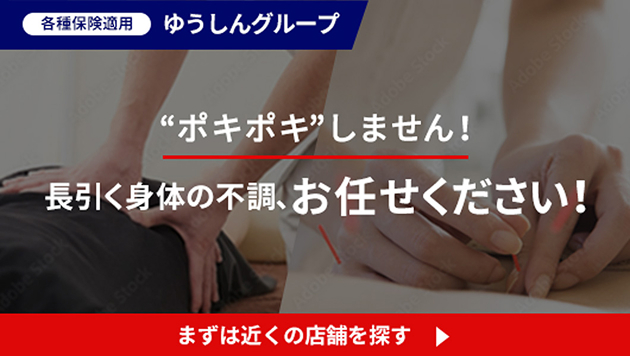

突然腰に激しい痛みが走り、動けなくなった経験はありませんか。ぎっくり腰は、誰にでも起こりうる身近なトラブルです。病院に行くべきか、安静にすべきか判断に迷う中で、自己流の対処で悪化させてしまう方もいます。今回は、ぎっくり腰の際に避けるべき行動や正しい対処法、予防のポイントまでを解説します。
目次
ぎっくり腰になった場合の対処法

ぎっくり腰になった直後は、間違った対処をすると症状を悪化させるおそれがあります。ここでは、発症当日から翌日以降にかけて、状況に応じた正しい対処法を紹介します。
当日~翌日の場合
ぎっくり腰を発症した当日から翌日にかけては、痛みが強く、無理な動作が悪化の原因になります。
まずは安静にして、腰に負担をかけない姿勢で休むことが大切です。無理に動こうとしたり、マッサージなどで刺激を与えたりするのは控えましょう。
また、炎症による熱感がある場合は、氷枕や保冷剤などで患部を冷やすと炎症を抑えるのに役立ちます。
反対に、熱感がなければ温めたほうが、筋肉がゆるみやすく、痛みが軽減する場合もあります。判断が難しい場合は、温めてみて痛みが強まらないかを確認し、楽になるようであれば温める方法を選びましょう。
そのほか、緊張で筋肉が硬直していることも多いため、深呼吸を意識してリラックスするのも効果的です。
症状が少し落ち着いてきたら、無理のない範囲で整形外科や接骨院で状態を確認し、今後のケアについて相談することをおすすめします。
翌日以降の場合
ぎっくり腰の痛みが少し和らいできたら、無理のない範囲で身体を動かし始めましょう。ずっと横になったままでいると筋肉が硬くなりやすく、回復が遅れるおそれがあるためです。まずは軽いストレッチなどから取り入れ、徐々に動ける範囲を広げていくことが大切です。
痛みが落ち着き、腰に強い刺激を感じなくなったら、少しずつ日常生活に戻していきましょう。ただし、症状が軽減しても油断は禁物です。中腰やねじった姿勢、急な動きは避け、背筋を真っすぐに保つことを意識してください。
また、痛みが緩和した後も、適度な運動やストレッチを継続することで、筋力と柔軟性が高まり、腰への負担が軽減されます。
ぎっくり腰になった際にやってはいけないこと

ぎっくり腰の直後に誤った対応をすると、痛みが強くなったり長引いたりする原因になります。ここでは、症状を悪化させないために避けるべき行動を具体的に紹介します。
患部を強く刺激する
ぎっくり腰の直後は、患部を強く刺激する行為を避ける必要があります。特に注意したいのが、強いマッサージです。一時的に気持ち良く感じることがあっても、筋肉や靭帯が炎症を起こしている状態では、刺激がかえって悪化につながる可能性があります。
痛みがある部位を手で強く押したり、叩いたりするのもNGです。押したり叩いたりしても痛みを和らがず、むしろ組織を傷つける可能性があります。
ぎっくり腰は状態によって適切な対応が異なるため、自己流の対処ではなく、専門家に相談するのが安全です。
まずは腰に余計な負担をかけないよう安静を保ち、必要に応じて整形外科や接骨院で状態を確認しましょう。
無理な動作をする
ぎっくり腰を起こした直後は、無理に身体を動かすのは非常に危険です。腰の筋肉が損傷しているため、立ち上がったり歩いたりすると、炎症や痛みがさらに悪化するおそれがあります。
痛みの緩和を急ぐあまり動こうとすると、逆に症状を長引かせてしまうこともあるため注意が必要です。特に急な動作や身体をひねるような動きは、腰に強い負担をかけてしまいます。
トイレに行くなどやむを得ず動かなければならない場面では、可能な限り周囲の協力を得ながら、無理のない範囲でゆっくりと身体を動かすようにしてください。
一人で無理をして動こうとすると、転倒やさらなる損傷につながる危険もあります。まずは安静を優先し、痛みが落ち着くまでは極力動かずに過ごすことが大切です。
アルコールを摂取する
ぎっくり腰の直後にアルコールを摂取するのは避けたほうが無難です。アルコールには、血行を促進する作用があるため、患部の炎症がひどくなり、痛みが強まる可能性があります。
また、飲酒によって判断力が鈍ることで、普段なら慎重に動くはずの場面で無理な姿勢をとってしまい、腰の状態を悪化させるリスクも考えられるのです。
さらに、痛み止めなどの薬を服用している場合、アルコールと併用することで副作用が出やすくなったり、肝臓への負担が増えたりするおそれがあります。そのため、ぎっくり腰の早期回復には、アルコールを控えることが望ましいです。
代わりに、水分をしっかり補給し、炎症を抑える効果が期待できる栄養バランスの整った食事を意識しましょう。
ぎっくり腰にならないための予防策

ぎっくり腰は、腰の関節や椎間板(軟骨)、腱、靭帯が損傷することで、痛みが生じるとされています。一度発症すると再発しやすいといわれており、普段の生活の中でも、腰に負担をかけないよう意識することが大切です。
ここでは、日常で実践できる3つの予防策を紹介します。
予防策1|適度に運動をする
ぎっくり腰の予防には、適度な運動を継続していくことが重要です。運動不足が続くと、腰を支える体幹の筋力が低下し、ちょっとした動作でも腰に負担がかかりやすくなります。
特に腹筋と背筋のバランスが崩れるとリスクが高まりますが、多くの場合、腹筋の弱さが原因となるため、背筋ばかりを鍛えるのは逆効果です。
予防には、軽めの腹筋トレーニングや有酸素運動がおすすめです。ウォーキングや水泳といった身体への負担が少ない運動が効果的で、継続すれば筋力と柔軟性の両方が高まり、腰の安定性が増します。
はじめから激しい運動を行うのではなく、身体に合わせて徐々に強度を上げていくことがポイントです。毎日の生活に運動とストレッチを取り入れるだけでも、腰への負担は大きく軽減されます。
予防策2|長時間同じ姿勢を取らないようにする
長時間同じ姿勢で過ごすことは、ぎっくり腰になる大きな原因のひとつです。デスクワークなどで椅子に座り続けると、腰まわりの筋肉が硬直しやすくなり、血流も悪くなります。血流が悪くなると、疲労物質が溜まりやすくなり、腰への負担が増すのです。
また、あぐらや足を組む姿勢、猫背など身体がゆがんだ状態を続けると、脊柱のバランスが崩れ、さらに腰に負荷がかかります。
脊柱は、身体を支える柱の役割を果たしているため、姿勢のゆがみは腰痛のリスクを高めます。できれば30分に1度は立ち上がり、軽くストレッチをして筋肉をほぐすようにしましょう。
また、日常的に正しい座り方を意識することで、腰への負担を減らせます。
予防策3|腰に負荷がかかるような動作を避ける
腰に強い負担がかかる動作を避けることも、ぎっくり腰の予防には欠かせません。例えば、腰を曲げたまま重い物を持ち上げると、腰椎や周囲の筋肉に急激な負荷がかかり、ぎっくり腰を招きやすくなります。
荷物を持ち上げるときは、膝をしっかり曲げて身体全体を使い、下腹部に力を入れて腰椎のS字カーブを保った姿勢で行うのが理想的です。中腰のまま作業を続けたり、不安定な姿勢で物を持ち上げたりするのも避けましょう。
また、激しいくしゃみや咳による一瞬の衝撃も、腰を痛めるきっかけになることがあります。咳やくしゃみをするときは、お腹に力を入れて腰を安定させる意識を持つと安心です。
さらに、朝起きるときに勢い良く身体を起こす動作も危険です。まず横向きになり、腕で支えながらゆっくりと起き上がるようにしましょう。
まとめ
ぎっくり腰は、間違った対処や生活習慣によって悪化や再発を招きやすい症状です。早期の正しい対応と、日常の中での予防が重要です。もし腰に強い痛みを感じたら、無理をせず、信頼できる接骨院でのケアを検討してみてください。
ゆうしんグループでは、痛みの少ないソフトな施術に加え、AI姿勢分析によって不調の原因を見える化しています。丁寧なカウンセリングで、一人ひとりに合った最適な施術の提案が可能です。
再発予防まで視野に入れた対応をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。